第79回 4章 ガスの科学と物質の階層構造
|
|
| 4−2 階層と尺度 |
|
| 4−2−2 異なる階層の観測・波の観測 |
|
|
|
|
| 4−2−2 異なる階層の観測・波の観測 |
| (3)光と電気による観測 |
 |
光は、ほとんどの場合、電気に変換されて検知される。光と電気の変換反応は、比較的古くから知られているが、はじめは、電気と温度や圧力との関係を示す現象から見出された。
18世紀、物質が温度の変化に応じて電気的ポテンシャルを生ずることが、カール・フォン・リンネ(1707〜 1778年、スウェーデン)によって見出された。カール・フォン・リンネは「分類学の父」であり、最も有名な生物学者のひとりであるが、当時の博物学は、生物も無生物も研究対象としており、リンネも植物界・動物界・鉱物界の研究を行っていた。
リンネの鉱物の研究によって温度と電気には何か関係があることは見出されたが、温度変化を電圧として取り出して研究するところまではできなかった。 |
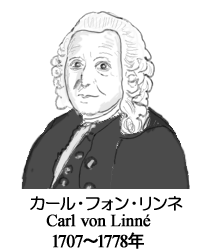 |
|
| 焦電効果の発見 |
| |
 |
19世紀になって、アントワーヌ・セザール・ベクレル(1788〜 1878年、フランス)は、これを温度変化による誘電体の分極の変化として研究、再発見した(1819年)。
ベクレルが発見したこの現象は、後にデビッド・ブリュースター(1781〜1868年、スコットランド)によって「焦電効果(pyroelectric effect)」と名付けられた(1824年)。 |
|
| 圧電効果の発見 |
| |
 |
ベクレルの実験からは、大きな成果は得られなかったが、60年後、ジャック・キュリー、(1856〜1941年、フランス)とピエール・キュリー(1859〜1906年、フランス)兄弟によって結晶構造体の焦電性が確認され、「圧電効果(piezoelectric effect)」として理論化された(1880年)。ただし、一般的には、圧電現象は、1819年にベクレルによって発見されたと記録されている。
圧電体に圧力を加えると分極が現れる圧電効果は、圧電素子(ピエゾ素子)として実用化され、現在では、点火装置、ソナー(SOund Navigation And Ranging、SONAR)、スピーカー、水晶発振器、アクチュエーター、各種電子回路、各種センサー、インクジェットプリンターなど様々な機械に応用されている。 |
|
| ベクレル効果の発見 |
| |
 |
アントワーヌ・セザール・ベクレルが行った応力と電気を結びつける焦電効果の実験はうまくいかなかったが、これらの研究は、電気化学の発展に大きく寄与し、アントワーヌは、息子のアレクサンドル・エドモン・ベクレル(1820〜1891年、フランス)とともに、溶液中の金属電極に光を照射すると起電力が生じる現象、光起電力効果(photovoltaic effect)を発見した(1839年)。
ベクレル親子が発見した光起電力効果は「PV効果」とも「ベクレル効果」とも呼ばれている。
アレクサンドル・エドモン・ベクレルは、PV効果に対するスペクトル特性や太陽光の研究も行っており、これは現在の太陽光発電のスペクトル特性研究につながっている。また、ガイスラー管を用いた蛍光灯も発明している。(ただし、実用化に貢献したのはエジソンの部下であるニコラ・テスラやダニエル・ムーアらである) |
|
| 光電効果の発見 |
| |
ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツ(1857〜1894年、自由ハンザ都市ハンブルク)が、光電効果(photoelectric effect)を発見(1887年)した。物質にエネルギーの大きな光(紫外線)を当てるとそこから電子が飛び出す現象が見出された。
ヘルツは、電磁波を発見(1885年)、電磁波が何もない空間中を伝播し、その速度が光速度に等しいことなどを発見した。ヘルツが発見した光電効果は、後にアインシュタインによってその機構が説明された。
|
 |
 |
|
| |
なお、ボーアの原子模型を検証してノーベル物理学賞を受賞(1925年)したグスタフ・ルードヴィッヒ・ヘルツはハインリヒ・ヘルツの甥、グスタフの息子カール・ヘルムート・ヘルツは、医療用の超音波検査装置を発明し。ハインリヒ、グスタフ、カールの3人のヘルツが、電磁波、物質波、音波の分野にそれぞれ名を残したが、SIの周波数の単位となっている「ヘルツ(Hz)」はハインリヒ・ヘルツに因んで制定された。 |
| ベクレル効果の発見から100年、ようやく光発電が可能となった |
| |
光と物質の相互作用が次々と明らかになっていったが、アントワーヌ・セザールとアレクサンドル・エドモンのベクレル親子が発見した光起電力効果(PV)は、その後、電解質溶液だけでなく、半導体のpn接合や、半導体と金属との接合部などでも発生することが分かった。
しかし、光が電気に変換される現象は、その変換効率が極めて低いため、視覚信号への変換としては十分であっても、電力として取り出すことは難しく、光を電力に変換する発電機が発明されるのは、発見から100年も後のことである(1954年、米国ベル研究所)。
半導体を用いて、光起電力を外部に取り出すことで得られる「光電流(光電子)」を利用する機器をPVセル(photovoltaic cell)と呼ぶ。太陽電池(solar cell)と呼ぶこともあったが、光起電力を用いる発電は、光源を太陽光に限定するものではなく、また電池という呼び方も誤解されやすいため、この言葉はあまり使われなくなってきている。英語のcellを電池と訳すと「太陽電池」や「燃料電池」のようになるが、いずれも電力変換器(発電機)であって蓄電池ではないため、最近は、cellを日本語で電池と訳さずに、PV(photovoltaics)やFC(fuel cell)と記号といった言葉で示されることが多くなっている。従来は太陽光発電機器の展示会と呼んでいたものを最近では、PV展、PVエキスポなどと呼ぶようになり、PVは日本語として定着しつつある。その起源は、アントワーヌ・セザールとアレクサンドル・エドモンのベクレル親子が180年前に発見したPV効果、ベクレル効果である。 |
| 放射性物質、放射性元素(後の放射性同位体)の発見 |
| |
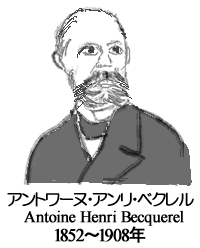 |
アレクサンドルの息子のアントワーヌ・アンリ・ベクレル(1852〜1908年、フランス)はウラン鉱から放射線を発見した(1896年)ことで知られる。
アントワーヌ・アンリ・ベクレルのファーストネームが、ベクレル効果で知られる祖父アントワーヌ・セザール・ベクレルと同じであるため、放射線を発見したベクレルは、ミドルネームをとって、アンリ・ベクレルと呼ばれることが多い。
アンリ・ベクレルが放射線(後にα線)を発見する前年の1895年には、ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン(Wilhelm Conrad Rontgen、1845〜1923年)がX線を発見、第一回のノーベル物理学賞を受賞している(1901年)。 |
|
| |
20世紀の科学は、量子論、相対論の二大理論に加えて放射線の発見とその利用によって支えられ、ガスの科学(分子、原子、原子核の科学)も発展していったが、X線の発見者レントゲンは、もともとはガスの研究者である。空気分離プロセスの発明者のひとりであるカール・フォン・リンデは、ルドルフ・クラジウスに習い、熱力学を実学に応用していったが、クラジウスの研究室の系列で学んだレントゲンは、同じように熱力学やガスの研究を行っていたが、ガスの物性の研究中に放電実験から偶然X線を発見し、その後の科学の発展に大きな影響を与えた。 |
| |
フランスのベクレル家は有名な物理学の家系である。アンリ・ベクレルの息子ジャン・ベクレルも結晶や電場を専門とする物理学者で、アインシュタインの相対性理論をフランスに広めることに貢献している。アインシュタインは当初ドイツ語で論文を書いていたため、他の言語圏においてその理論を知らしめる優秀な学者がいたがフランス語圏ではベクレルがその役割を果たしている。
19世紀から20世紀初頭のベクレル家は、4代に渡る物理学一家である。ベクレル効果(PV効果)は、アントワーヌ・セザール・ベクレルとアレクサンドル・エドモン・ベクレルが発見、太陽光発電の研究に贈られる「ベクレル賞」はアレクサンドル・エドモン・ベクレルに因むものである。SIにおける放射能の単位「ベクレル(Bq)」はアントワーヌ・アンリ・ベクレルに因む。 |
| |
 |
 |
アンリ・ベクレルが発見したウランから発せられるX線に似た透過力のある光線は、当初は謎につつまれていた。これを学位論文のテーマにしたいと考えたマリ・キュリー(1867〜1934年、ポーランド)がアンリに依頼、マリはアンリを指導教官として放射線の研究をすることになった。
この研究が、新元素ラジウムの発見、放射線の発見につながり、アンリ・ベクレル、、マリ・キュリー、ピエール・キュリー(1859〜1906年、フランス)はともにノーベル物理学賞を受賞した(1903年)。 |
|
| |
なお、キュリー家も科学の一家で、ピエールの兄ジャックは物理学者、ピエールとマリ・キュリー夫妻はノーベル物理学賞、マリ・キュリーはノーベル化学賞、娘のイレーヌ・ジョリオ=キュリーと娘婿のフレデリック・ジョリオ=キュリーはノーベル化学賞を受賞、ジュリオの子どもたちも、核物理学者(エレーネ・ランジュバン=ジュリオ)や生化学者(ピエール・ジュリオ・キュリー)である。 |
| 見えない脅威、微生物 |
| |
世界には、見えないものや聞こえないものがたくさんあり、人々は昔から、その正体不明の何かに囲まれていると考えてきた。見えない何かを見えるように、自然を探求し、理解しようと、観察道具を作り、見えない階層を理解する科学を発展させてきた。自然は、下の階層に支配されるという仕組みからは逃れることはできないが、観察して、そこにある法則を調べ、対処する方法が考えられてきた。
自然界には伝染病という見えない脅威がある。ヒトの体には病原菌やウィルスなどの外敵を排除するための免疫力がある。しかし、それだけでは対抗できないこともある。欧州で14世紀に起こったペストの流行では全人口の1/3という莫大な犠牲者を出し、17世紀、フックやニュートンの時代の英国でも多くの犠牲者を出した。ボイルが錬金術を化学に変え、フックが高性能の顕微鏡を製作し、科学の時代が始まったが、当時の科学ではまだペストの正体を突き止めることはできず、見えない大きな脅威が存在した。
それから200年もたって、19世紀の末、香港からインドシナに広がったペストを追って、アレクサンドル・イェルサン(1863〜1943、フランス)と北里柴三郎(1853〜1931年、日本)が渡航、それぞれペスト菌を観察、発見した。ペスト菌の大きさは、約1μm程度、現在の電子顕微鏡の技術があればはっきりと映像として観察ができる。しかし、当時は。観測方法も対処法も十分に確立されていない時代である。先駆的な研究者によって見えない脅威、ペストが発見された。 |
| |
人間が本来持つ免疫力に任せるべきという考え方もあるかも知れないが、人々は微生物の脅威をそのまま受け入れることのではなく、見えないものの正体を探し、対処する方法を研究してきた。古来より様々な薬が考案され、20世紀になって、抗生物質が発見された。アレクサンダー・フレミング(1881〜1955年、英国)がペニシリンを発見(1928年)、人工の抗生物質の大量生産に成功し、多くの人々が感染症から救われ、フレミングはノーベル医学生理学賞を受賞した(1945年)。
病原体の感染の影響を防いだり和らげたりするために、世界各地で予防接種という方法がとられている。現在、日本では乳児・幼児が就学前に受ける定期・任意のワクチン予防接種は17種類ほどもあり、ヒブ、小児用肺炎球菌、4種(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)、結核、麻しん・風しん、日本脳炎、ロタ、B型肝炎、おたふくかぜ等、接種スケジュールを考えるだけでも簡単ではない。それだけ多くの種類の見えない脅威にさらされており、多くの対処法がみつかっているということである。 |
| 見えない脅威、電気と放射線 |
| |
自然は、けっしてありのままの姿を我々の前に現すことがない。病原菌やウィルスだけでなく、電気や電波、電磁波、放射線など、見えない自然の脅威に曝されている。
自然界には、電気や電磁波、放射線が大量に存在し、文明社会は、さらに大量の人工の電気や電磁波を生み出している。その結果、電気や電波によって多くの便利な道具が生まれている。もし電気の脅威を減したければ、人工の電気の利用を止めればよいが、我々の文明は、既に電気があるリスクよりも、電気がないリスクの方がはるかに大きくなっているため、人工の電気を全て止めることはできない。見えない脅威を理解し、利用することによって現代社会が成り立っている。 |
| |
電気の利用は、20世紀後半からの文明社会を大きく進歩させたが、電気(電子)の階層は、極端に小さく、電気の実体を理解することは非常に難しい。ヘンリー・キャヴェンディッシュ(1731〜1810年、イングランド)とシャルル・ド・クーロン(1736〜1806年、フランス)によって電磁気学におけるクーロンの法則が見出されたのは18世紀後半(1785年)であるが、これが理論的に解明され、ジェームズ・クラーク・マクスウェル(1831〜1879年、スコットランド)によってマクスウェルの方程式が導かれたのは、80年も後、19世紀の中盤(1864年)である。 |
| |
19世紀、マクスウェルは、ファラデーの電磁誘導の法則、アンペールの法則(電流による電場の発生)、ガウスの法則(電場)とガウスの法則(磁場)の4つの法則を統合し、古典電磁気学を確立した。マクスウェルの方程式には、磁束保存の式、ファラデー−マクスウェルの式(電磁誘導)、ガウス−マクスウェルの式(電荷)、アンペール−マクスウェルの式(変位電流)といった重要な式が含まれ、これらの方程式から得られる帰結によって、電場と磁場が電磁場として統合され、光が電磁波であることも導かれた。
しかし、それを記述する時空には、それまで信じられてきたニュートン力学が適用できないという重大な問題が提起され、この課題が、アインシュタインの特殊相対性理論によって解決されるのはさらに40年も後、20世紀になってからのことである。 |
| |
人々が、雷や静電気によって電気の存在を知ったのは、紀元前ともいわれる。電気は、250年前のクーロン、200年前のファラデー、150年前のマクスウェル、110年前のアインシュタインと長い時間をかけて解明され、現代物理学の成果として、その利用技術は、20世紀後半から21世紀にかけて急速に発展した。
見えない脅威「電気」も、現在ではなくてはならない文明の道具となっている。 |
| |
| |
表-光電効果と熱電効果 |
年 |
人物 |
発見 |
内容 |
18世紀中盤 |
カール・フォン・リンネ |
後の焦電効果の発見 |
|
1819年 |
アントワーヌ・セザール・ベクレル |
焦電効果の再発見 |
温度変化による誘電体の分極の変化 |
1821年 |
トーマス・ゼーベック |
ゼーベック効果 |
温度差が電圧に直接変換される熱電効果 |
1834年 |
ジャン=シャルル・ペルティエ |
ペルティエ効果 |
異種金属接合に電圧をかけると、接合点発熱吸熱が起こる熱電効果 |
1839年 |
アントワーヌ・セザール・ベクレル
アレクサンドル・エドモン・ベクレル
|
光起電力効果、
ベクレル効果
|
光を電気に変換、PV発電 |
1851年 |
ウィリアム・トムソン(ケルビン卿)
|
トムソン効果 |
温度の差がある2点間に電流を流すと発熱吸熱が起こる熱電効果 |
1880年 |
ジャック・キュリー、
ピエール・キュリー |
圧電効果 |
ピエゾ素子 |
1887年 |
ハインリヒ・ヘルツ |
光電効果 |
物質にエネルギーの大きな光を当てると電子が飛び出す |
1895年 |
ヴィルヘルム・レントゲン |
X線の発見 |
気体の研究中に放電を行っている時に発見 |
1896年 |
アントワーヌ・アンリ・ベクレル |
放射線の発見 |
ウランのアルファ崩壊 |
1905年 |
アルベルト・アインシュタイン |
光量子仮説 |
波であると思われていた光に粒子性を導入 |
1916年 |
ロバート・ミリカン |
光量子仮説の実証 |
光電効果の定量的実験 |
1923年 |
アーサー・コンプトン |
コンプトン効果 |
電磁波が粒子性をもつことを証明。光量子仮説が認められ、光量子には光子という名前がつけられ、光は光波と光子の性質を示す量子となった。 |
|
| |
|